摂食障害とは
福井大学医学部附属病院
神経科精神科
福井県吉田郡永平寺町

「食べ方」や「体重・見た目」へのとらわれが強くなりすぎて、体や心に深い影響が出る病気です。たとえば、「太るのが怖い」「もっと痩せたい」と思い込み、無理に食事を減らす、食べた後に吐いてしまうなどです。一方で、繰り返し大量に食べてしまって止められないこともあります。こうした行動は見た目の問題ではなく、実は“心のSOS”としてあらわれるケースが多いです。
様々な種類
神経性やせ症(AN)
体重がかなり減っていても、「自分は太っている」と感じて、もっとやせようと食事を極端に制限します。
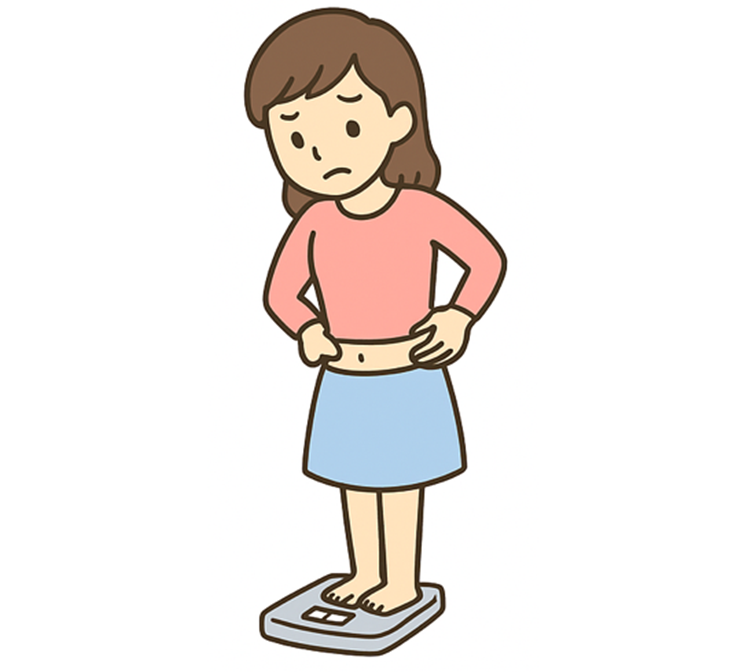
神経性過食症(BN)
たくさん食べた後に、吐いたり、下剤を使ったり、運動しすぎたりして体重増加を防ごうとします。

過食性障害(BED)
止められない「むちゃ食い(過食)」を繰り返しますが、吐いたりしないため体重が増えてしまうこともあります。
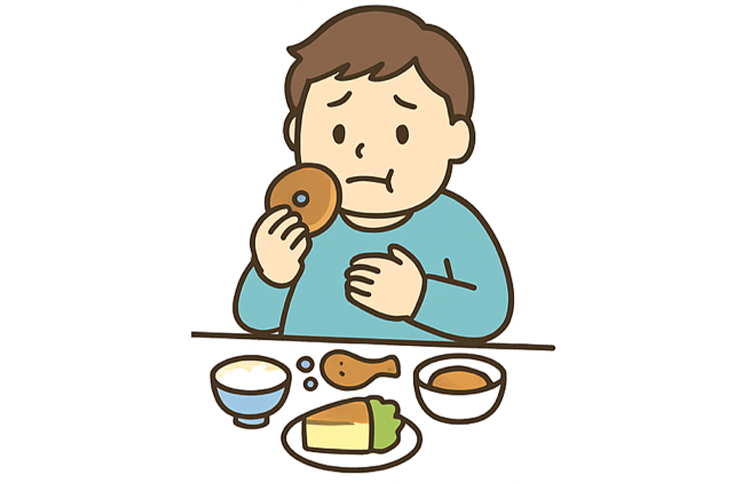
回避・制限性食物摂取障害(ARFID)
体重や見た目へのこだわりはなく、特定の食べ物の味や食感が苦手で、食事の種類や量が極端に限られます。小児期からみられることが多いです。

どのくらいいらっしゃるか
摂食障害は、特に10代から20代の女性に多い病気です。
| 神経性やせ症 | 0.3〜1%(約100人に1人) |
|---|---|
| 神経性過食症 | 1〜2%(約50人に1人) |
| 過食性障害 | 2〜3%(約30人に1人) |
たとえば、30人の中学校の1クラスに1人以上が何らかの摂食障害を経験するとも言われています。最近は、小学生や男性にも広がっていることがわかってきました。
主な症状
「太っている」と思い込み、ダイエットをやめられない
食事の量を減らす、または大量に食べて後悔する
食事を避ける、家族との食事を嫌がる
無月経(女性)、便秘、寒がり、疲れやすい
気分の落ち込み、イライラ、不安感
原因と背景
摂食障害は、「こうすれば発症する」というはっきりした原因はわかっていません。以下のような、いくつかの要因が重なって発症するのではないかと考えられています。
| 性格的な傾向 | まじめ、完璧主義、自分に厳しい |
|---|---|
| 人間関係やストレス | 学校でのトラブル、進学・就職の不安 |
| 家族関係 | 干渉が強すぎる、または関心が薄い |
| 社会的な影響 | SNSやテレビで「やせている方が美しい」とされる風潮 |
| 脳の働きや遺伝的な影響 | 神経伝達物質の関与が指摘されています |
治療と支援
摂食障害の治療では、身体と心の両方を回復させることが大切です。
- 医師による体調管理と必要に応じた入院
- 心理士による心理療法
- 管理栄養士による栄養サポート
- 家族への心理教育と支援
回復には時間がかかることもありますが、早めの相談が大きな助けになります。
福井大学医学部附属病院での取り組み
当院は、福井県摂食障がい支援拠点病院として活動しております。
以下のホームページには、病気について、治療について、支援について、詳しい情報が載っております。ご参照いただけますと幸いです。
https://fukui-edsupport.jp/
更新:2025.08.25
